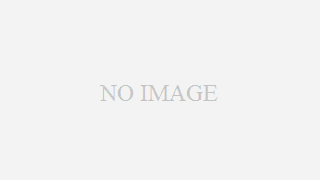 衛生管理者
衛生管理者 第1種・一種衛生管理者おすすめテキスト(問題集・参考書)比較レビュー
衛生管理者の勉強を始めて、まず悩むのがテキスト選びですよね。本屋に行くとさまざまな種類のテキスト(参考書・問題集)が並んでますし、私も色々悩みました。このサイトの管理人が第1種・一種衛生管理者に一発合格したおすすめのテキスト(参考書・問題集...
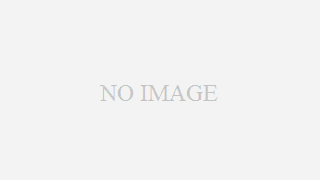 衛生管理者
衛生管理者 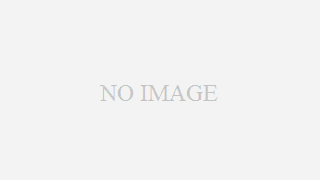 毒劇物取扱責任者
毒劇物取扱責任者 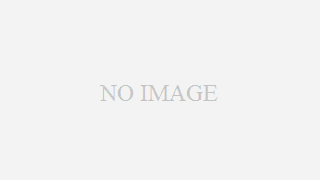 エネルギー管理士
エネルギー管理士 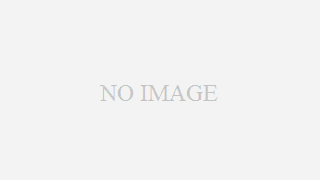 資格全般・勉強法
資格全般・勉強法 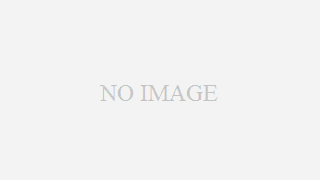 毒劇物取扱責任者
毒劇物取扱責任者 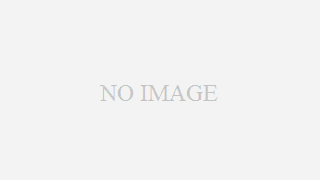 エネルギー管理士
エネルギー管理士 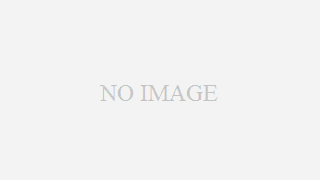 環境計量士
環境計量士 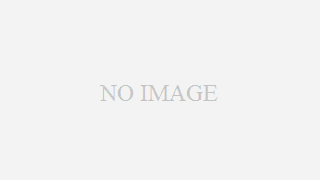 公害防止管理者
公害防止管理者 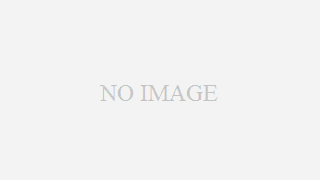 資格全般・勉強法
資格全般・勉強法 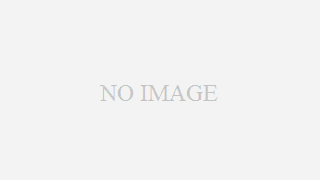 公害防止管理者
公害防止管理者